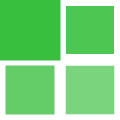ゆるい読書会@とっとり vol.5報告「悲しみの歌」
10月某日に行われたオンライン読書会「ゆるい読書会@とっとりvol.5」は、遠藤周作の「悲しみの歌」を課題図書として開催された。
小説の主な登場人物は、ある暗い過去をもつ医師・勝呂と、勝呂の過去を執拗に取材する新聞記者・折戸、奇妙な外国人ガストン。実はこの小説は「海と毒薬」の続編ともいうもので、戦時中の某大学医学部での生体解剖事件に関わった医師のその後、という物語となっている。
折戸が最初に勝呂に過去の事件について問い詰め「なぜ、関わるのを拒まなかったのか?」と問い詰めたとき、勝呂はこう答える。
「そうねえ。自分でも、よく、わからんねえ。おそらく、疲れていたんだろう」
この答えに折戸は憤慨する。まるで責任逃れのような言葉と聞こえたからである。
しかし、折戸の人生というのは何の迷いもなく、まっすぐに一直線のようにのびるハイウェイのように、挫折を知らなかった。彼は、「人間の悲しみ」というものを知らなかったのだ。
ガストンというのは、浮浪者のようにその日暮らしをしている奇妙なフランス人である。彼が思い煩うのはいつも、名もなき弱き存在であり、彼は勝呂が背負っている暗い悲しみにも気づく。
“彼はさっきから前に歩いている勝呂の背中がひどく孤独なのに気づいていた。顔はどんなに笑っていても、人間の無防備な背中はその人の心をそのまま現わすものなのだ。”
遠藤周作の本小説は、医師でありながら過去に人を殺めることに加担し、今でも妊娠中絶術に携わることに苦悩し続ける勝呂と、彼を追い詰める「正義」を振りかざす者たち、そして彼の深い悲しみに気づき、彼の苦しみを少しでも和らげようとするガストンをめぐって、読者をその結末まで引き込んでいく。
読書会には医師や助産師、学生など、7名が参加した。
この本のテーマとして
「悪とは何か」
「正義とは何か」
「人間らしさとは」
「誰が人間を裁くのか」
などが挙げられた。
生体解剖という絶対悪のような事件を起こした医師である勝呂に、同情あるいは共感の余地があると感じた者が多かったようだ。
医学者でありながら、自分たちのいわば先輩であるような医師が犯した戦争犯罪は、もし自分が同じ立場だったら拒否できるのか、という問いを突きつける。もちろん、組織の論理や時代の論理から、断れなかったと考えるのは難しくない。しかしながら、本書のテーマは一貫して、絶対悪の立場であるはずの勝呂が心清き人に見え、彼を追い詰める記者・折戸が悪に見えることである。つまり、悪とは一義的に決められるものではなく、その時代の規範や、あるいは立場・状況によって見方が変わってくるということだ。また、誰がその人間の悪を裁くのか、裁けるほど「清き」人間などいるのか、という問題にも話題は及んだ。
新聞記者・折戸の人生は挫折なき、成功者のそれであり、また社会悪を追求し報道する義務があるというエリート的な正義感に燃えているがゆえに、人の悲しみに盲目となっていることが議論となった。成功者であること自体は罪ではない。しかし、そこに悪があるとしたら、「自分は絶対に正しい」という驕りや、報道によって出世したいという利己心を交えながらもそこに自ら目をつぶっている狡猾さではないか。つまり、そういった「不透明さ」というものには悪の要素があるのではないか。
また、筆者が個人的に感じた本小説のリアルさは、勝呂の「おそらく、疲れていたんだろう」という言葉に代表される。
人間はおそらく、すべての瞬間において合理的に判断し、合理的に行動しているということはありえない。自分の気持ちとは矛盾するような行動をとってしまった、なぜか分からないけれどもある重大な行動を起こしてしまったということがあるものである。そんな人間存在の矛盾に満ちた「非合理性」を本小説は表現しているように思える。
アルベール・カミュの「異邦人」に出てくるムルソーは、なぜ殺人を犯したのかを裁判で問われ「太陽が眩しかったから」と答える。その非合理性、不可解性は、世間を怒らせ、彼を死刑においやるのである。
参加者の議論は、ガストンは何を表現しているのか、というところで意見が分かれた。ガストンは、キリスト的存在を表していると考えられたのだが、ガストンの存在だけリアルでない、人間ばなれしていると感じた読者が多かったようだ。遠藤周作は、なぜ本作のようにリアルな設定の物語に、ガストンという超人間的な存在を持ち出したのであろうか。
筆者の考えでは、人間が犯してしまった殺人のような重大な罪は、誰によって何をもって贖われるのか、という永遠の問いが、ガストンの存在に集約されていると感じる。殺人や虐殺、生体解剖という罪は、論理的に考えれば、何によっても償われるものではない。しかし、そのような者が、自らの死以外で救われるとしたら、キリスト的存在以外にあり得るのか。そのアポリアを考え続けたのが、遠藤周作なのであり、あえて人間離れしたガストンという存在を表現したことが、彼のテーゼの明快な提示なのではないかと考えるのである。
(孫)