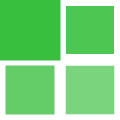医療人文学への誘い——治す医療から、ともに「共感」する医療へ
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
私たちは病院を訪れるとき、たいてい「体の不調」をなんとかしてほしいと願っています。熱が下がること、痛みがとれること、病気が治ること。それが医療の役割だと、私たちは自然に信じているのかもしれません。 けれども、医療がそれだけでは足りない場面に、私たちはしばしば出会います。
たとえば、治療を終えた人が「もう治ったと言われても、どう生きていけばいいのかわからない」とつぶやくとき。あるいは、高齢の親を介護する人が「医療は何もしてくれない」と涙ぐむとき。そこには、薬や手術では届かない、もっと人間的な苦しみや問いが横たわっています。
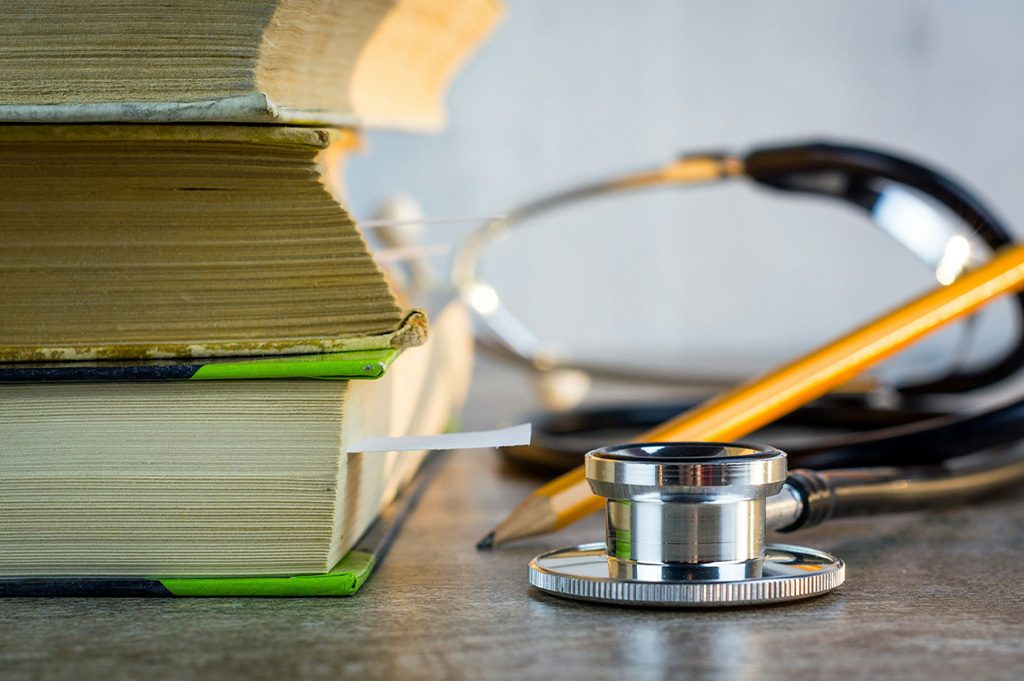
医療人文学とは何か
医療人文学(Medical Humanities)とは、こうした「治療」では答えきれない問いに向き合おうとする学問です。医学と人文学──文学、哲学、芸術、倫理など──のあいだに橋をかけ、病や死、生きる意味、他者との関係についてあらためて考える手がかりを与えてくれます。
たとえば、ある医学生が黒澤明の映画『赤ひげ』を観て、医師と患者とのあいだに流れる「沈黙」の意味について考えはじめました。医療の現場では、症状や検査結果を言葉で伝えるだけでなく、相手の沈黙に耳を澄まし、言葉にならない思いを感じ取る力が求められます。これはまさに、文学作品を読むときに私たちが行っている「行間を読む力」と通じるものです。
また、哲学は医療に本質的な問いを投げかけます。たとえば、「よい生とは何か」「自分らしく生きるとはどういうことか」。延命治療をめぐる葛藤や、認知症の人の尊厳について考えるとき、私たちは単なる医療的判断ではなく、「人間とは何か」という根源的な問いと向き合うことになります。
もちろん、現代医療は科学によって大きく進歩してきました。画像診断、遺伝子医療、AIによる診断支援など、私たちの命を救ってくれる頼もしい技術が次々と生まれています。しかし同時に、技術が進めば進むほど、「人間を診る」という視点が見失われる危うさもはらんでいます。 病を抱える人は、単なるデータや症例ではなく、「この私」として生きている存在です。その人の物語に耳を傾け、背景や暮らし、価値観を理解しようとする営みの中に、医療人文学の意義が息づいています。

アートや哲学を通して医療をひらく
医療人文学は、医師や看護師だけのものではありません。患者や家族、介護者、市民すべてに開かれた領域です。近年では、市民と医療者がともに語り合う「対話の場」や、演劇や映画を通して病と生を考えるワークショップが各地で広がりつつあります。
私自身もこれまでに、市民と医療者が語り合う「みんくるカフェ」、路上で屋台をひきながら対話を促す「モバイル屋台カフェ」、映画を鑑賞し語り合うワークショップ、即興演劇(プレイバックシアター)を活用した市民参加型の取り組みなどを実践してきました。これらの活動を通じて、医療を専門家だけが担うものではなく、市民や患者が主体的に関わり、ともに考え、形づくっていけるものへとひらいていきたいと考えています。
人は誰しも、いつか病を抱え、老い、そして死を迎えます。そのとき、私たちを支えるのは、医療制度だけではなく、他者との関係性や、自分の人生に意味を見出す力です。医療人文学は、そうした「生きる力の回復」に関わる学びでもあるのです。 とくに、アートの力や哲学の深いまなざしは、技術の進歩だけでは救いきれない「人間の生の困難」に光をあててくれます。映画、演劇、音楽といったアートは、希望や癒しの源になることがあります。また、「この私にとって世界はどう意味づけられているのか」という問いを探求する現象学という哲学は、患者の世界に寄り添う視点を与えてくれます。

医療人文学のこれから
鳥取大学地域医療学講座では、これまでも医学生や医療従事者、市民向けに、医療人文学に関するさまざまなワークショップを開催してきました。2022年に制作した短編映画『うちげでいきたい』は、全国で170回以上上映され、市民と医療者が看取りや終末期医療について語り合う貴重な機会となりました。また、現在も続いている「ゆるい読書会」では、毎回文学作品などを取り上げ、人間の生と死にまつわる問題を参加者とともに自由に語り合っています。
今後は、鳥取県立美術館や鳥取民藝美術館との連携、湯梨浜町のミニシアターや小さな書店との協働による企画、あるいは医療従事者が哲学者とともに「現象学」を学ぶプログラムや、臨床事例を哲学的に振り返るワークショップなど、新たなプロジェクトも予定しています。 こうした医療人文学の学びと実践を通じて、「治す」医療から、「ともに感じ、ともに考える」医療へ。そうした転換に少しでも貢献できればと願っています。医療に携わる人はもちろん、そうでない人も、一度立ち止まり、「人が人を癒すとはどういうことか」を考えてみる。そんな時間を持つことが、これからの医療を変えていく一歩になるのではないでしょうか。
Author:孫 大輔
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。