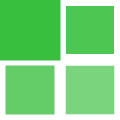「第2回医学教育分野別認証評価」を受審しました(7月1−4日)
鳥取大学医学部医学科は、2025年7月1日から4日にかけて「第2回医学教育分野別認証評価」を受審しました。本講座からは私(谷口)と孫准教授が担当教員として参加しました。
分野別認証は7年前に第1回を受審し、その際には本学の医学教育におけるさまざまな課題が指摘されました。今回の評価は、その後の改善の進捗を含めての審査であり、担当教員だけでなく医学生へのインタビューも行われるなど、包括的な視点からの評価となりました。
私たちが関わっている地域医療教育の分野については、鳥取県や県内の自治体と交流しながら教育を推進している点や、県からの寄附講座設置に際して医学部予算から専属教員を配置している点が評価されました。一方で、今後使命や学修成果を改訂する際には、患者や地域医療の代表者など、より広い関係者から卒業生の実績やカリキュラムに対するフィードバックを求めることが望まれるとの指摘がありました。
面談の場では、地域医療教育が熱心に行われており学生にも内容がしっかりと伝わっていること、日野病院や大山診療所といったサテライトでの実践が高く評価できることが確認されましたが、同時にプライマリケアを実践している現場での臨床実習をさらに充実させてほしいとの要望も寄せられました。また、学外実習施設での指導医のFDが不十分で大学の意図が十分に伝わっていない可能性や、医学生が電子カルテ記載など実践的な臨床にもっと関われるよう工夫を求める声もありました。
全体としてはおおむね好意的に評価いただけたと感じており、審査委員長の筑波大学・前野哲博先生からも「熱心に教育されていますね!」とのお声掛けをいただきました。今回の経験を励みに、今後もさらに地域医療教育の充実に努めてまいりたいと思います。
(追補:正式な受審結果の評価報告書より)
- 総評として、鳥取県や県内の自治体との交流等を通して地域医療教育を推進している。一方で、国際的に活躍する医療人のキャリア形成や、多職種連携の実践に関する教育カリキュラムを充実すべきである。
- 教育プログラムでは、行動科学、社会医学、医療倫理学、医療法学のカリキュラムを、現在および将来的に社会や保険医療システムにおいて必要になると予測されることに従って修正することが望ましいと。
- 私が担当したエリア7(教育プログラム評価)では、使命と学修成果に照合して教育プログラムの効果と適切性を判断する情報を定め、それを系統的に収集・分析してカリキュラムに反映すべきとの指摘があった。また、教育プログラム評価を行う組織は、カリキュラムの実施の一部である学生の評価を行う組織とは独立しているべきである。また、教育プログラムのモニタと評価に学生が実質的に関与すべきであること。患者、地域医療の代表者等、より広い範囲の教育の関係者に卒業生の実績ならびにカリキュラムに対するフィードバックを求めるべき。
やはり地域医療教育では一定の評価をいただいたが、教育プログラム全体の評価と改善において、使命に照らして整合性があるのか、教員だけでなく学生や患者や地域医療代表者など広い範囲で教育成果を評価してもらう仕組みづくりの必要性を指摘されました。今後の鳥取大学医学部の教育プログラムについて大きな宿題をもらったと考えています。(谷口)