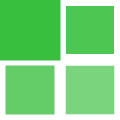『コンパッション都市』との出会い
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
総合診療研修でお世話になっている鳥取市立病院の櫻井先生の誘いで、私は米国のエンド・オブ・ライフケアの専門家であるアラン・ケレハー先生が書いた『コンパッション都市-公衆衛生と終末期ケアの融合-』という本の読書会に参加しています。難解な本ですが、参加者同士で話し合いながら読んでいる事で、楽しく読み進められています。
本では西欧の中世~現代に至るまでの死生観の変遷、そしてそれらを踏まえ死を共同体の中で共に悼む(compassion)事が述べられていました。私はふと「西欧と日本とでは文化が違うのだから死生観も違うはずであり、そうなると西欧の死生観に立脚して語られているコンパッション都市の議論も日本の文化に適合した形で再構成する必要があるのでは?」と疑問に感じ、臨床業務などの合間をぬって学びを深める事にしました。
フランスの中世~現代の死生観の変遷(フィリップ・アリエス)
フランスの社会学者、フィリップ・アリエスは著作『図説 死との文化史』の中で西欧の死生観の特徴について興味深い記述を残しています。
18世紀のフランスでは家が臨終の場でした。そこでは死にゆく人が主導権を持ち、臨終の秘蹟を得るため家に司祭を呼ぶ事や、家族・友人を呼び和解する事を要望しました。それらが済むと言葉を発することを自ら止め臨終を待ちました。人々は「孤独に死ぬこと」を恐れ、自らの死の過程が家族・友人・社会共同体と共有されることを望みました。
19世紀後半には家族の愛情が重視され、「死に至る過程」の苦痛を患者が感じないよう(患者は死を予感しているのに)家族・友人・医師が「治る病気だ」と患者に嘘をつくようになりました。臨終の場は家でしたが、臨終の時に呼ばれるのは親族のみになっていました。その一方、終末期に医療を受けるかどうかの選択権は患者が持っていました。
20世紀後半に米英を中心に「死のタブー化」が生じ、患者は病院で医学の管理の下、極限まで延命治療を受けて死んでいきました。その背景には家は「幸福な場」であり、死の様な「悲惨なもの」が存在してはならない、という思想がありました。
日本の中世~近世の死生観(立川昭二)
日本の死生観について知るため、文化史家・立川昭二の『日本人の死生観』を手に取りました。この本では先人の作品を通してうかがい知れる生き様・死に様が紹介されていました。
鎌倉期の歌人・西行と江戸期の俳人・小林一茶の死生観の対比は興味深かったです。西行は武士という地位や妻子を捨てて出家し、
小林一茶も西行と同様に愛妻・愛息の死、
現代の死生観の動き
さて、話を現代に戻しましょう。アリエスの死後、西欧では死のタブー化を乗り越え「死」をもう一度取り戻そうとする動きが起き、社会学者のトニー・ウォルターは「死の復活」と呼びました。この「死の復活」にはキュブラー・ロスの「死のアウェアネス運動」や『コンパッション都市』などのレイトモダン的な動きと専門家による「死の医療化・商業化」にも警戒し、自分らしい死の迎え方を追求しようとするポストモダン的な動きがあります。こうした「死のタブー化」や「死の復活」は日本でも見られる動きです。
「死の復活」の動きの一方で、「死の医療化」の根強さを感じさせた出来事もあります。コロナ禍の初期には、西欧でも日本でも「医学」に基づき社会が要請する形で、コロナに罹患した患者が「医学」の名のもとに、家族から引き離され孤独に死ぬことを強要されました。イタリアの哲学者アガンベンは現代では「むきだしの生」が強調され、医学的管理による死の扱いの正当化に対して抗しがたい状態に陥っていると批判しました。
日本的『コンパッション都市』はどうすべきか
『コンパッション都市』では住民が喪失を共に悼む(Compassion)ことを重視しています。日本には「常世信仰」があり死者の霊魂が山や海に還っていく、という捉え方もあります。よって日本的コンパッション都市では、西欧的な悼む感情に加え、亡くなったものに対する敬い、親しさ、感謝などの感情を共有する事が重要と私は考えます。こうした取り組みは既にあり、阪神大震災や東日本大震災の犠牲者の追悼式などの場で見る事ができます。
問題は戦後に進んだ地方から都市部への人口移動によるコミュニティの喪失です。災害などの悲劇的な物語を共有していない人同士が、喪失を共に感じ合う関係性を結ぶのは至難の業です。お上が「共同体が大切です」
以上、私が死生観やコンパッション都市に触れ、考えた事を述べさせて頂きました。皆さんにとって、この文章が新たな視点を提供するキッカケとなれば幸いです。
【参考文献】
- アラン・ケレハー著,竹ノ内裕文・堀田聰子訳.コンパッション都市-公衆衛生と終末期ケアの融合-.東京,慶應義塾大学出版界株式会社.2022.
- フィリップ・アリエス著,福井憲彦訳.図説死の文化史-ひとは死をどのように生きたか-.東京,日本エディタースクール出版部.1990.
- 立川昭二.日本人の死生観.東京,三松堂株式会社.2018.
Author:小原亘顕
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。