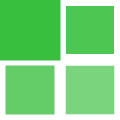僕がカフカを読むわけ
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
今、自分の中でフランツ・カフカが熱い。
最近できた新しい本屋に立ち寄ったとき、何気なく手にとったのが『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)だった。
カフカか……高校生のときに『変身』を読んで「ワケワカランなぁ」と思い、それ以来、彼の作品を読むことはなかった。
とりあえず、その本をめくってみるとこんなことが書いてある。
将来にむかってつまずくこと、これはできます。
いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです。
これは、カフカが自分の恋人フェリーツェに送った手紙の中の言葉である。
なんと絶望的であろうか。
カフカの絶望ぶりは度を越しており、彼の絶望の言葉に触れると、どんなネガティブな人でも「そこまで自分は絶望していない」と思えるほどである。
カフカの絶望名人ぶり
彼の人生は、すべてが空回りし続けた、いわば絶望続きの人生だった。
今でこそ世界的な文学者として有名なカフカだが、彼の小説は一部
仕事はうまく行かず、従って仕事に行くときはいつも憂鬱だった。
二回婚約した恋人フェリーツェとは、二回婚約破棄となり(しかも、自分から婚約破棄を言い出した!)、結局独身のまま死んだ。
父親との関係に問題を抱えており、それは死ぬまで克服できなかった。
体が弱く、いつも自分の体調がすぐれないという感覚を抱いていた。
自分のやることのすべてに自信がなく、自己肯定感はとてつもなく低かった。
そんな「絶望名人」の彼が書いた『変身』や『城』といった小説は、今では世界的な名作とされており、ノーベル文学賞作家たちがこぞって絶賛する作品群なのである。
一体、彼の小説の何が、そこまで人を惹き付けるのだろうか。
カフカの『城』を読む
そこで、カフカの長編小説の代表作とされている『城』を読んでみた。
なんだこれ。めちゃくちゃ面白い。
出だしから面白いのである。高校生だった自分が初めてカフカを読んだときの印象とまるで違う(そのときは『変身』を読んだのであるが)。
当時のカフカ小説の印象は「奇妙なワケワカラナイ小説」。人間の「不条理」を描いているのかもしれないけれど、とても共感しにくい。いきなり自分が巨大な虫になって……。一体なぜ、こんなにも奇妙な設定の、奇妙な物語にする必要があったのか。
『城』に出てくる主人公のKは、おそらくカフカ自身である。彼が、ヨーロッパの(と思われる)ある町の「城」に測量技師として赴くところから話が始まる。
しかし、一向に「城」の中には入れない。入れないどころか、自分を呼びつけたのが誰なのかもはっきりせず、自分の直接の上司(クラム氏)は、なんとドアの鍵穴越しにちょっと垣間見ることしかできない。「城」のまわりの住民たちはKに対してよそよそしい態度を取り続け、木で鼻をくくったような対応に、Kの精神は削られていく。そんな物語である。
官僚制に対する批判?それとも……
芥川賞作家の平野啓一郎氏は、カフカの小説を「官僚制主義に対する批判」と読み解く。
たしかに、『城』とそれを取り巻くさまざまな制度や人間関係は、巨大な官僚機構を思わせるような描写となっている。そう考えると非常に共感もしやすい。官僚主義の硬直した態度や制度に対して怒りを感じるのは、いつの時代もそれほど変わらないからだ。
でも、ちょっと違うような気もする。
カフカはおそらく、人生そのものを「自分には少しも居場所のない世界」「どこまでいっても居心地の悪い世界」と感じていたのではないか。カフカにとっては、人生そのものが官僚機構のようなものだった。
彼が感じていた絶望感や疎外感というのは、例えばアルベール・カミュが感じていた抑圧や徒労感とは完全に別物である。カミュの表現する世界も「不条理」をテーマにしているが、彼には「反抗する人間」という理想像が見えていたように思う。
カフカにとっては、この世界はどこまでいっても奇妙で、居心地が悪く、自分の身体が自分のものでないような、自分の話している言語を誰も理解してくれないような、つまりは、自分そのものがこの世界にとっての異物であるような、そんな感覚だったに違いない。
それは「絶望」というよりも、絶対的な「疎外感」、あるいは、死ぬまで続く「めまい」のような感覚に近いかもしれない。
今、カフカを読む意義とは
そして今、時代のほうが、カフカに追いついてきたようにも思う。
カフカが感じていた「疎外感」や「めまい」のようなものは、例えば、社会的マイノリティや、周縁化された人々の当事者感覚を的確に表現してはいないだろうか。
そうした人々が感じ続けているのは、自分が社会にとっての異物であるような奇妙な感覚、すなわち『変身』において、ある朝、巨大な虫になってしまったグレゴール・ザムザのような感覚であろう。
文学は面白い。それは、希望よりも絶望、高揚よりも苦悩、快楽よりも不快を描くからである。そこに人は、人間存在の本質を見るのである。
Author:孫 大輔
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。