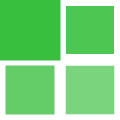キャリアについて考える
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
先日、教室の中井先生とともに、医学科1年(新入生)のキャリア入門の講義を行った。中井先生は体調不良のためオンラインで講義に参加してくれた。私はおもに自分が医学部を卒業してからのキャリア経緯と転機となったエピソードなどを紹介し、自分のキャリアを決めた理由などを交えつつ話した。いっぽう、中井先生は総合診療医として活躍するまでの経緯を話してくれた。学生時代にサークル活動のフィールドワークで地域住民と交流したり、臨床推論サークルやイギリス研修などの経験が、その後の進路に大きな影響を与えているようであった。
私の場合、学生時代は社会医学・地域医療、卒業後は臨床研修→内分泌専門医→基礎研究→留学→帰国して糖尿病→地域疫学調査→地域医療学講座という、ちょっと普通とは変わった道筋をたどっている(普通というのは、専門分野を決めたらそれを一生かけて深めること)。いろいろなことに手を出して中途半端にならなかったかといえば、その傾向はあるかもしれない。
でも、人生には選択肢を突き付けられる瞬間というのが何度かある。そのとき私は直観にしたがって決断した、決して先々のことを計算して決めたわけじゃない。面白そうだ、できるかもしれないと思えば、迷わず挑戦してきた連続が私のキャリアということになる。
クランボルツの理論とキャリアアンカー
興味深いのは中井先生も、友人とのつながりや好奇心にしたがって、新しい分野である総合診療医をめざすことを決めたとのこと。そして講義の中で、偶然だが二人とも、クランボルツの計画された偶発性(Planned happenstance theory)のキャリア論に言及した。
クランボルツは、予期せぬ出来事が個人のキャリアを左右する、予期せぬ出来事を避けるのではなく、起きたことを最大限に活用すること、偶然を積極的につくりだしキャリア形成の力にすることが重要と考えた。
そのためには以下の5つの資質、
- – 好奇心(Curiosity): 新しい学習機会の模索
- – 持続性(Learning): めげない努力
- – 柔軟性(Adaptability): 信念、概念、態度、行動を変える
- – 楽観性(Persistence): 新しい機会を「実現可能」と捉える
- – 冒険心(Risk Taking): 結果が不確実でも行動に移す
が大切であると主張した。
この理論を知った時、私は深く納得した。これこそが自分が実践してきたことだし、基本的なキャリアへの向き合い方だと思ったのだ。
私の場合、好奇心、持続性、楽観性、冒険心は人一倍あると思っている。
私のキャリアは行き当たりばったりで、決して学生たちに自慢できるようなものではないと思っていたけど、クランボルツの理論を知ると、まさにこの考えに近い発想で人生を歩んできたと思えたのだ。現代はVUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の時代であり、長期的な社会の将来像を描きづらい状況だからこそ、クランボルツのキャリア論に意義があるという主張も腑に落ちるものだった。
さらに中井先生は、重要な局面で決断せねばならないとき、キャリアアンカーが重要であるといわれた。
キャリアアンカーとは、アメリカの心理学者エドガー・シャインが提唱した概念で、個人が何かを選択しようとしたときに、その人が最も放棄したがらない「欲求」であり「軸」となるものをいう。何がしたいのか、何が求められるのか、何に価値を感じるか、これらの中核にあるのがキャリアアンカーである。各人が計画された偶発性の姿勢でのぞみ、重要局面ではキャリアアンカーを意識しながら決断すること。そういうプロセスが大事であるということを学生へ投げかけた。
「正解の道」ではなく「正解にする姿勢」
もうひとつ、中井先生の話で印象に残ったのは「正解の道を選ぶことよりも、選んだ道を正解にしようとすることが大切だ」という言葉である。とても納得できる言葉だ。
私の場合、人生の分岐点で自分の直観にしたがってきたが、新たな道というのはそう簡単ではないことも多かった。というより、始める前には見えなかった困難が次々に襲ってくるという感じに近い。
でも、その一つ一つの障壁に向き合い乗り越えていくことで、成果も見えるし自分の成長が実感できる。 まさに、「自分の選んだ道を正解にしようとすること」が、人生を前進させる原動力になってきたと思う。
講義のあとで質疑応答の場面となったが、最近の学生は目立つ事を嫌うのか、手をあげて質問をしない。そこでLiveQというアプリで質問を集め、二人で答えることにした。
質問の多くは総合診療医の仕事ややりがいに関するものだった。そのほかに、「自分は変わらない日常が好きなので新しいことは敬遠するけど、どうしたら挑戦できるか」、「今までの人生でいちばん後悔したことはなにか」など、突っ込んだ質問もあがっていた。
その時私は思い出した。自分も学生時代は不安で仕方がなかったことを。失敗したくないと思っていたことを。医学部に入ってひと安心と思っていたら、サークル活動やクラス内の人間関係など、予想もしなかったストレスにさらされた。真面目に勉強すれば人並の成績はとれると思っていたが、たいした勉強もせず要点を理解し、空いた時間をサークル活動やバイトに費やしている同級生たちを横目でみて、「自分もできるかも」と思ったのが大間違いだった。
生活が滅茶苦茶になり、講義も休みがちで自堕落な学生生活を送っていた。それは苦々しい日々だった。 自分より頭のいい人は山ほどいるし、精神的に大人な人も多い。自分の存在価値はいったい何なのかと問い続け、もがき苦しんだ時期でもあった。自分が望んで入った地域医療サークルも、「きみはどう考えるのだ」という問いかけの連続で少々うんざりしていた。
だから、「学生時代は楽しかったね、青春は二度と戻らないから」と言われても、私は全くピンとこないのである。
学生時代は暗黒や灰色で包まれ、自分が何者でもないことを突き付けられた、二度と戻りたくない時代である。 あの時の自分が、いまの私のキャリア講義を聞いたらどう感じただろうか。「失敗を恐れず挑戦することで未来が開ける」だって、「そりゃ成功したあなたならそう言えるだろうよ」と皮肉っていたのではないか。
オンボロな過去が導いた、キャリアの転機
一昨年から医学生を連れてインドネシアでのプライマリケア研修に行っている。
インドネシアに行き、診療所などを訪問して向こうの医学生と議論したりするので、この研修に参加する学生たちは、志が高くやる気にあふれていて優秀な人が多い。楽しいエピソードもたくさんあるが、ここでは学生たちとの話題を紹介しよう。
懇親会で学生時代の思い出話となり、私が「学生の頃はよく講義を休んだりして不真面目だった」というと、みな一様に驚いた顔をする。私は一見すごく真面目そうに見えるし、学生への講義スタイルも「硬い」ので、過去の不真面目な学生時代が想像できない様子である。
私は図に乗って「講義を休んで海や山に行ったり、酒を飲んだりしていた」と、オンボロ学生時代の話を自慢気にしゃべっていたのだけれど、学生たちはどう感じたのだろうか。「そんな不真面目な学生時代を過ごしたのに、最終的に地域医療の教授になったんかい、なんでやねん」と思ったかもしれない。ある学生から「先生はいつから態度が変わったのですか」と聞かれた。
学生の頃を振り返ると「勉強するのが当たり前」「医療は人のためにすべき」「地域医療はこうあるべき」という、べき論ばかりで自分を縛っていた。それがつらくて、卒業前のあるとき、「もう、べき論はやめる、自分のやりたいことを好きなようにやる」と決めたのだった。いわゆる優等生の「承認欲求」に苦しんでいたのだが、このときはっきりとそういう態度と決別したのだった。
卒業後に臨床医の仕事にも今一つ自信がもてずモヤモヤしていたときに、私は基礎研究(実験)というものに出会った。
培養細胞を相手に遺伝子導入などの分子生物学的手法を用いて自分が考えた仮説を検証するのである。深夜の実験室で、顕微鏡下に浮かびあがった蛍光免疫染色のグリーンに輝く細胞の美しさ、暗室の赤色光のもとでフィルムにうかびあがるバンドの数々、ひとつひとつのプロセスが美しく感動的で、一気に魅了された。
実験と研究が楽しくて次から次に学びたいことが増えていった。ものごとの捉え方の筋道がわかると、基礎研究でも臨床でも地域医療でも、目先の分野が変わっても別に怖くない、気がついたら今ここに立っているというわけだ。だからあのとき、もし研究に出会わなかったら、自分を導いてくれた上司に出会えてなかったら、まったく違うキャリアを選んだのではないかと思う。
クランボルツの計画された偶発性のキャリア論は、ある意味で「大人」の考え方である。余裕があり懐の深い人でないとなかなかできないし、根拠のない自信や楽観性がなければ難しいことだ。
私自身がこの方法を取れるようになったのは、研究を続けて成果を認められ仕事に手ごたえを感じるようになってから後の時代の話である。たぶん30代の半ばを過ぎてからのことではないのか。それまでの私は、「大人」ではなかったし、俯瞰的に自分を観察することができなかった。
研究に出会うまでは、クランボルツの理論を実践するための資質である、好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心、どれひとつとして備えていなかったと思う。でも人生終盤の今になって振り返ると、人間は何かをきっかけにたしかに「変わることができる」と思うのである。
講義のなかでは、そういう情けなくてオンボロの学生時代は触れなかったので、学生たちは私がもともと自信家で挑戦が好きな人なのだろう、と誤解するかもしれない。
「ちがいます、オンボロでした。その後に好きなことを見つけ、それを徹底的に深めて自信がついたから変われたのです。」
私の学生時代は暗かったけれど、自分はいったい何者なのか、どうありたいのか、何ができるのかできないのか、そういう問いに向き合う大切な時間でもあった。
もし、もういちどキャリアの話を学生にする機会があるなら、そういうオンボロの学生時代とその後の生き生きワクワクの時代の転換点を、すこし詳しく紹介してみたいと思うのである。
Author:谷口 晋一
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。