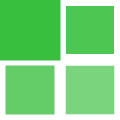ゆるい読書会@とっとり第3回:鷲田清一の『「聴く」ことの力』
8月16日に、ゆるい読書会@とっとり Vol.3をオンライン開催しました。
今回の課題本は鷲田清一さんの『「聴く」ことの力—臨床哲学試論』(阪急コミュニケーションズ, 1999年)です。
著者の鷲田清一さんは朝日新聞1面コラム「折々のことば」を連載していることでも有名ですが、専門は臨床哲学・倫理学の先生。現象学・身体論を専門としており、ファッションの研究もしているという面白い方です。
この本は、その哲学の先生が一般向けに書いた本で、「聴く」という行為についてさまざまな哲学的視点から考察を深め、「臨床哲学」という新しい地平を開いたということでも有名です。第3回桑原武夫学芸賞を受賞しています。
哲学者が書いた本でありながら、その中身は、宇野千代さんの人生相談コラムの文章、阪神淡路大震災でボランティアに行ったとき被災者との会話、ある人類学者の父と障害をもった子との会話など、具体的なエピソードから分かりやすく書き起こしています。
かつ、哲学者らしく、メルロ=ポンティの現象学的身体論、レヴィナスの他者倫理の哲学など、さまざまな哲学的概念を縦横無尽に引きながら、従来の哲学に欠けていた〈聴く〉ことについての視点、言葉のテクスチュア(きめ・肌ざわり)を感じるための「非方法の方法」などについて考察を深めているという本です。
読書会のディスカッションでは「とにかく難しい」という感想が最初に出ました。
やはり、哲学者の書く本は一般向けの本といえど、難しいのか……。
主催者としては「今回は選書に失敗したか…」と冷や汗ものでしたが、参加者同士の対話が徐々に進むにつれ、議論は深まっていきました。

「ホスピタリティと傷つきやすさ(ヴァルニラビリティ)の表裏一体性が興味深かった」
「なぜ看護師は燃え尽きやすいのか:仕事モードと日常モードでの「聴く」ことの違い」
「ケアとは『時間をあげる』ことだというのが印象深かった」
「〈聴く〉ことの本質を表すエピソードとしての、会話の無意味性、その相互行為としての視点が面白い(子供に差し出された手をすっとつかむ父親)」
「〈聴く〉ことは、ただそこに「居る」ということ、これは東畑開人の『居るのはつらいよ』でも描かれていた」
こうしたやりとりの中で、ある参加者がこんなエピソードを披露してくれました。
「それほど親しくもない友人から、あるとき流産したということで長文のLINEが送られてきた。すごく共感してしまい、長文の返事をしたが、それっきりになってしまった。『当て逃げ』されたようなモヤモヤが残った。あれは何だったのか」
その「友人」との距離感にもよるのではないか、そもそもその友人は聴いてもらいたかったのか吐き出したかっただけなのか、自分の中の専門職としての部分と友人としての部分の線引きがあいまいだったから?、向こうからの「応答」の欠如がモヤモヤにつながった?、などさまざまな意見が。
また、参加者に医療者が多いという観点から考えると「そもそも私たちは『相手の話を聴くべき』という善良性がインストールされているので、そこから距離をとること自体が難しくなってはいないか」という意見も出ました。
〈聴く〉という行為は、心を込めて相手に一杯のお茶を差し出すような行為なのではないか。そこでは「言葉」自体はあまり重要ではなく、その「迎え入れられた」という感覚が本質なのではないか。
その一杯のお茶を差し出すという象徴的行為に込められた「ホスピタリティ」と、それがゆえの「傷つきやすさ」。しかし、おそらく人間が生きていく上で、誰かと心から交流する、自分をひらく、ということは、傷つきやすさ(可傷性=ヴァルニラビリティ)と不可分なのだろう。
そんな議論に関連して、ある医学生がとても印象的なことを言ってくれました。その言葉を紹介して本レポートを締めくくりたいと思います。
「私は、地域医療実習で日野病院に行って初めて、『人』と向き合って〈聴く〉ことができた気がします」
(孫)